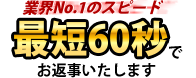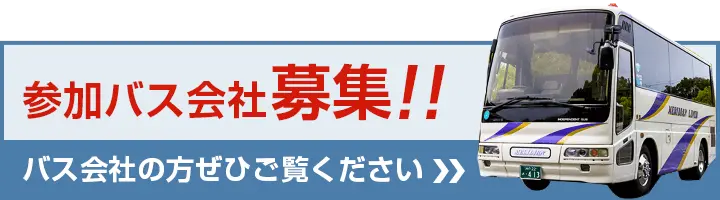社内イベントや社員旅行で移動手段を手配しないといけない幹事さん、サークル合宿やゼミ旅行の移動手段を検討している学生さんなど、貸切バスというものが団体移動に便利ということを聞いたが、そもそも貸切バスがどんなサービスなのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では貸切バス専門のバス旅ねっとが「貸切バス」について、チャーターバスとレンタルバスの違い、貸し切らずに不特定多数で利用する乗合バスとの違いを、法的な定義も含めて解説します。また知っているようで知らないバスという乗り物自体の歴史についても深堀りしますので、現在のバスについての認識が少し変わるかもしれませんよ。
貸切バスとはどんなサービス?
貸切バスとはバス車両を運転手付きで占有チャーターできるサービスで、自らが運転するレンタルバスやレンタカーとは異なるサービスです。法人利用だけでなく個人利用も可能で、未成年の学生さんでも法定代理人(保護者など)の同意があれば契約できます。
どんなバスがチャーターできるの?

バスというと子供の頃に修学旅行や遠足などで乗った背の高い観光バスを思い浮かべるのではないでしょうか?旅行会社が企画する果物狩りバスツアーやカニ食べ放題バスツアーなどでも同じような観光バスが使われていますよね。これらの大きなバスは貸切バスとして個人でチャーターできます。
またスクールバスや福祉車両などで使われているマイクロバスや、14人乗りのハイエースコミューターのような乗用車に近いサイズのミニバスなど、送迎バスも運転手付きでチャーターできます。
さらに街中を走っている背の低いワンステップやノンステップの路線バス車両も、車両を保有しているごく一部のバス会社で貸切バスとしてチャーターすることが可能です。
借り上げバスとは何が違うの?
全国の自治体が実施している旅行助成金制度では、貸切バスのことを「借り上げバス」と呼んだり、バスチャーター費用のことを「借上料」と呼ぶことがあります。これは元々助成金制度の対象だった旅行会社が、企画に使用するバスをバス会社から丸ごと1台”借り上げる”という意味で、貸切バスと同じ意味です。
「借り上げ」という言葉自体の意味は、「政府や目上の者が、民間や目下の者から借りること」なので、旅行会社とバス会社の関係にマッチしていたのでしょう。貸切バスは個人団体や一般企業でも利用できるため、助成金の対象を旅行会社に限定しない場合にも「借り上げ」という文言がそのまま使われています。
他に「借り上げ」という言葉が使われているのは不動産業界です。一般企業が不動産会社と法人賃貸契約した物件を従業員に貸し出すことを「借り上げ社宅」、不動産会社がマンションオーナーと1棟丸ごとの管理契約を結び入居者に貸し出すことを「一括借り上げ」と言います。
貸切バスはどんな時に使うもの?
貸切バスの行程はすべてオリジナルのオーダーメイドであるため、ツアーバスや路線バスと比べ自由度が高く可能性は無限大です。また移動中の車内は自分たちだけのプライベート空間のため、行程だけでなく車内での過ごし方も自由です。バス設備を使って研修ビデオを視聴したりカラオケ大会をしたり、移動時間を有効活用できますよ。そのため貸切バスプランは千差万別ですが、よくある利用シーンをお客様の属性でまとめていますので参考にしてみてください。
| 法人のお客様の 貸切バス利用 |
社員旅行 | 視察 | 研修 | 空港送迎 | ロケバス | 派遣スタッフ送迎 | 建設作業員送迎 | 定期契約送迎 |
|---|---|
| 法人顧客様への 貸切バス利用 |
展示会送迎 | 物件見学会送迎 | 自社イベント招待 | 就活イベント送迎 | イベント出演者送迎 |
| 学校法人や学生様の 貸切バス利用 |
試合遠征 | 修学旅行 | 遠足 | ゼミ旅行 | サークル合宿 | スキー・スノボ送迎 |
| 個人のお客様の 貸切バス利用 |
観光旅行 | 自治会旅行 | 結婚式送迎 | 葬儀法事送迎 | ゴルフ送迎 |
貸切バスの利用方法は?
貸切バスは自由であるものの、タクシーやレンタカーのように当日乗ってその場で好きな場所に行くということができません。貸切バスは安全管理の法令基準が厳しく、安全な時間とルートが設定された「運行指示書」通りにしか運行できないルールがあるためです。そのため貸切バスを利用するために事前予約が必須であることはもちろん、どこから出発してどこへ立ち寄りどこで運行を終えるか、運行指示書の元となる行程表の作成が必要です。
また貸切バスの料金はエリアごとに距離単価と時間単価それぞれに下限額が定められており、それを下回る安値で運行してはいけないというルールがあります。さらにドライバーの拘束時間についても労働基準法に基づくルールがあり、長時間・長距離の運行を計画しているとかなり高額になる場合があります。
このように貸切バスには複雑なルールが多いため、バス旅ねっとのように利用者とバス会社の間での調整交渉や行程表作成など、円滑な運行のためサポートを受けられるサービスを活用するのがおすすめです。まずは見積りを依頼してみましょう。
貸切バスの法律的な位置づけは?
貸切バスとしてチャーターできる種類には、送迎バス・観光バス・路線バスがあるとしましたが、これはあくまで車両タイプのお話です。貸切バスとは日本の道路運送法における事業形態の1つで、人を運ぶ旅客自動車運送事業は4つに分類されています。詳しく見てみましょう。
| 乗一般乗合 旅客自動車運送事業 | 路線バスや高速バスのように、運行ルートや乗降場所が予め決まっている運行形態です。 国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。 |
|---|---|
| 一般乗用 旅客自動車運送事業 | タクシー(流し営業)やハイヤー(完全予約制)のように、乗車定員が10名以下の車両を使用し、都度の個別契約で旅客を運送する事業です。 国土交通大臣の許可を受けることが必要です。 |
| 一般貸切 旅客自動車運送事業 | 観光バスやロケバスのように、国土交通省令で定める乗車定員以上の 車両を使用し、都度の個別契約で旅客を運送する事業です。 地方運輸局長の許可を受けることが必要です。 |
| 特定 旅客自動車運送事業 | スクールバスや従業員送迎バスのように、特定の運送需要者を特定の目的地へ運送する事業です。 国土交通大臣の許可を受けることが必要です。 |
このような事業区分があるため「◯◯バス会社」という名前だけを見ても、どの事業の届出をしているバス会社かはわかりません。乗合バス・貸切バス・特定バスすべての営業許可を得ている会社もあれば、いずれかに特化しているバス会社もあります。
そのため貸切バスを使いたい時は、個別のバス会社に1件ずつ問い合わせるよりも、バス旅ねっとのような全国のバス会社と提携している貸切バス手配サービス会社に相談いただいた方がスムーズですよ。
貸切バスは観光バスだけじゃない
法的な区分に「観光バス」というものはありません。観光バスとはあくまで観光を目的にした仕様で製造されたバス車両のことを指すため、それぞれのバス事業形態で観光バスは利用されています。
- 有名観光地で定期運行している観光ループバスは「乗合バス」
- 企業が契約した社員旅行のための大型バスは「貸切バス」
- 宿泊施設が契約した定期運行のシャトルバスは「特定バス」
レンタカー事業と自動車運送事業は異なります
貸切バス事業に近い事業形態として、自家用自動車有償貸渡事業=レンタカー事業があります。こちらの開業にも許可申請は必要ですが、車両を貸すだけの事業と、旅客を輸送する事業は責任の範囲が明確に違なるため、車両のナンバーが分かれています。

事業用車両の緑ナンバーは運送事業として国の認可を受けている証で、旅客運送だけでなく貨物運送でも使われています。
国の許可を得ずに、レンタカー事業の延長として白ナンバーのまま有償対価を得て運送を行うことは「自動車運送事業経営類似行為」という違反行為です。俗に言う白バス・白タク・白トラと呼ばれるものがこれにあたります。

ちなみに貸切バスでも利用される車両のうち、マイクロバスは運転手なしの車両のみでレンタルすることは可能ですが、大型バスや中型バスはレンタル利用できません。
それは法令で「自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、車両全長7m未満のもの)」と規定されているためです。
バス旅ねっとで手配する貸切バスはすべて緑ナンバーのきちんと許可を受けているバスです。マイクロバスのレンタカー利用と貸切バス利用はどちらの方がお得なのか?詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。
貸切バスと他のバスとの違い
バスでの移動手段がそもそもどんなものであるかを法的な区分から見てきましたが、ここで貸切バスの特徴を、他の旅客運送事業と比較したポイントで押さえておきましょう。

- レンタカーと違い運転手付きなので全員が楽に移動できる
- タクシーやハイヤーと違い大人数で移動できる
- 路線バスや高速バスと違い好きな場所ルートで移動できる
- 路線バスや高速バスと違い乗り換えなしで移動できる
- 乗合バスと違い不特定多数と接触せずに移動できる
貸切バスの歴史って実は長い
ここまで貸切バスとはどういう事業形態であるか、どんな特徴があるのか、どういう利用目的で利用されているのかをお話をしてきましたが、そもそも貸切バスというのはいつ生まれたのでしょうか?
バスについてちょっと興味が湧いてきたあなたのために、貸切バスの歴史についても少しふれてみようと思います。
そもそもバスはどこで生まれた?
バスの前にまず自動車の誕生について。世界初の自動車は1769年にフランスで二コラ・ジョセフ・キュニョーがつくった蒸気自動車です。1769年といえば日本ではまだ江戸時代。学生の頃に習った日本史の授業で同じ時期を思い起こしてみると、老中として活躍する田沼意次がやっと御用人になったのが1767年、杉田玄白が解体新書を書き始めたのが1771年ですね。日本ではまだまだ自分の足で歩くか馬に乗るかしかなかった時代に、ヨーロッパでは蒸気を使った乗り物が作られていたのは世界の大きさを感じます。そこから1886年には今の自動車の原形となるガソリン車が生まれ、その後ドイツやアメリカで研究が進み1913年に量産化に至りました。日本では1907年(明治40年)に国産発のガソリン車「タクリ―号」がつくられました。
そしてバスの起源はというと、車より前の馬車の時代になります。1662年にフランスでブレーズ・パスカルが考えた、定時運行する馬車に安価で乗り合いできるという「5ソルの馬車」です。その後1826年に「バス」という名称の語源となった馬車ができたと言われています。馬車乗り場の目印になっていた「オムネ」という店の看板の「OMNES omnibus(すべての人のためのオムネ)」という言葉から、乗合馬車のことを「オムニビュス(オムニバス)」と呼ぶようになり、省略して「バス」となったとか。現在では作品集の意味で使われているオムニバスの”バス”が乗り合いバスの語源だったんですね。
その後自動車の発展に合わせ、1831年に蒸気バス、1882年には電気トロリーバス、1895年にはエンジンバスが生まれました。今後も技術の進化にともなって脱炭素の次世代燃料で走るバスが増えていくことでしょう。
日本でのバス事業のはじまり
世界でのバス発祥の歴史からもわかるように、バスという乗り物の定義は、高価である馬車や車に、不特定多数の人が乗り合うことで、安価な運賃で運行できる路線バスの仕組みから始まったと言えるでしょう。
そして日本でのバス事業の始まりには諸説ありますが、日本バス協会がバスの日と定めている1903年(明治36年)9月20日に、京都市の二井商会が始めた堀川中立売~七条停車場、三条寺町~祇園石段下間を1区4銭で走らせた乗り合いバスが1番有力な説と言われています。運転手と助手の他に4名しか乗れなかったり、即日営業中止勧告が出されたりしたんですけどね。
日本最古の国産バスに今も会える

バスの日にもなった二井商会のバスを始め、他にもバス事業の起源とされる諸説の広島市や大阪市で使われたバスも、すべてアメリカ製の車両でした。日本初の国産バスは1929年(昭和4年)に誕生した「スミダM型バス」。製造したのは、現在もバス車両の主要メーカーとして知られる「いすゞ自動車」の前身である石川島自動車です。この車両は実装可能な最古のバスとして経済産業省の「近代化産業遺産」に認定されており、2011年には東京モーターショーのブースで出展されましたが、なんと今でも「いすゞプラザ」で展示されているため見ることができるんですよ。
バス事業者の統廃合へ
大正には鉄道事業者が、鉄道路線エリアを補完するためにバス事業を始めるケースが増え、1923年(大正12年)の関東大震災で被災した市営電車に代わる市民の足となったことをきっかけに、公営バス事業が始まりました。1925年(大正14年)には東京乗合自動車が定期遊覧乗合バスを始め、1928年(昭和3年)にはバスガイド付きの観光バスも登場しました。

昭和になるとバス事業者は乱立し、戦争を経て統廃合が繰り返されながら、1933年(昭和8年)の自動車交通事業法整備により、路線ごとに事業者が整理され、現在の路線バスのベースとなっています。
1950~1960年代(昭和20~30年代)にかけては、国産ディーゼルバスの普及と大型化によりバス事業は拡大し、地方のどの都市にもバスがあるだけでなく、旅行会社による団体貸切バス需要の高まりからバス業界は黄金時代を迎えたのです。
しかしながら高度経済成長下での鉄道路線拡充と自家用車普及に伴い、次第にバス離れの流れが起き、特に地方ではバス事業者の撤退や再編が相次ぎました。
こうして見ると時代の影響を強く受けていることがわかりますね。
長距離高速バスの誕生と競争加熱

1969年(昭和44年)に東名高速道路が開通し、長距離高速バスが運行するようになると、バス業界にはまた新たな流れが生まれます。1980年代(昭和60年代)後半になると夜行高速バスブームが起き、開業ラッシュとなったのです。
さらに2002年(平成14年)の規制緩和が拍車をかけ、旅行会社が企画する「高速ツアーバス」が誕生しました。多数の振興企業が高速バス市場に参入したことにより、過剰競争を生み出してしまいました。安価で多様なバスツアーができたこと自体は消費者にとって喜ばしいことだったのですが、旅行会社から低価格でのバス供給を強いられたバス会社の、コスト削減のしわ寄せはバス運転手に向かい、過労運転が常態化することで、重大事故を引き起こすまでに至ってしまいました。
その後2010年(平成22年)に国土交通省は、有識者による「バス事業のあり方検討会」を設置し、2012年(平成24年)には高速乗合バスと高速ツアーバスの仕組みを1本化しました。バス事業者に一定のハードルを課すことで、安定・安全かつ運賃変動性という、消費者に優しい仕組みになったのです。
観光バスを個人や団体で貸し切るスタイルへ
このようなバス事業の歴史を経て国土交通省が貸切バスに対しても動きました。2011年(平成23年)にはセーフティバス認定制度によりバス会社の安全管理を評価できる仕組みを導入。2014年(平成26年)には貸切バスの運賃・新料金制度により運賃の下限料金を設定したことで、バス会社やバス運転手が安全性を欠く不当な扱いを受けないようになりました。現在はバス業界全体が低価格競争を避け、安全性がより重視されるようになったのです。
どのバス会社で貸切バスを利用しても大きく料金が変わらない仕組みになったことから、消費者も激安の旅行会社を使うのではなく、自らが直接バス会社と契約する、個人利用や法人利用が増えました。
ですが個人で1件1件バス会社に問い合わせをすることは手間がかかるため、現在はバス旅ねっとのような貸切バス手配サービス会社を通しての利用が主流となっています。
さらに近年では2つの理由から、貸切バス利用が好まれるようになっています。
旅行の目的地の多様化には貸切バス
1つ目はSNSの普及です。これまでは人気の観光地というと、誰でも耳にしたことがあるような有名な観光地がメインとなり、観光旅行はお決まりの王道コースが決まっていました。ところが近年SNSで個人が絶景スポットなどを投稿するようになると、誰にも知られていなかったようなスポットが急に脚光を浴びるなど、人々が行きたいと思う観光スポットは多様化するようになりました。
そのため旅行会社が販売している観光ツアーや、公共交通機関で準備されている観光周遊バスでは、それらのニーズをまかなえなくなってきており、自由にコースをつくれる貸切バスの需要が高まっているのです。
不特定多数との接触を避けるには貸切バス
2つ目は新型コロナウィルスの蔓延です。一時の混乱は落ち着き、withコロナとして新たな行動様式が一般化してきました。普段の生活から感染リスクを下げるための行動に置き換わり、人々の移動手段の選択肢にも変化が出てきています。満員電車を避けて時差出勤をしたり、自転車通勤に切り替えたり。コロナ以降バイクの免許を取る人が増えているそうですよ。このようにこれまで使っていた公共交通機関よりも、よりプライベートな移動方法が好まれ、旅行でも団体ツアーに参加するのではなく、身近なグループで貸切バスを使うケースが増えているのです。貸切バスというと大きな大型バスのイメージが強いですが、用途や規模に合わせて様々な車種から選ぶことができるんですよ。
貸切バスについて法律と歴史の背景から解説してきましたがいかがだったでしょうか?バス旅ねっとは貸切バス専門の手配サービスとして2009年よりノウハウを積んできたサービスのため、全国の様々なケースでの実績が豊富です。似たようなサービスに一括見積もりサービスがありますが、こちらの最終的なやりとりはお客様とバス会社が直接行うものなので、複数のバス会社とのやりとりになると大変かもしれません。
バス旅ねっとはお見積りのご依頼から当日の運行やお支払いまで、窓口は一貫してバス旅ねっとだけです。ご要望に合わせて複数のバス会社で検討されたい場合や、数百名単位で複数バス会社からバス車両を手配するような場合でも、すべてバス旅ねっとの担当スタッフにお任せいただければOKです。最適でスムーズな貸切バス手配のため尽力させていただきますので、安心してご相談くださいませ。上記の情報がある程度決まられている場合はお見積りフォームよりのお問い合わせがおすすめです。