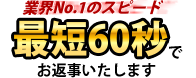社内の若手社員がミレニアル世代からZ世代へと変化していく中で、人事総務担当者のみなさんは採用活動や定着率の難しさを日々感じていることでしょう。しかし今は、待遇や福利厚生の充実といった目に見える要素だけで解決できる時代ではありません。大切なのは、いかに「会社の魅力」を伝えるかです。
そのために「企業ブランディングが必要」と聞くと、テレビCMや大規模な広告を思い浮かべ、「うちのような中小企業には難しい」と尻込みしてしまうかもしれません。しかし今の時代、消費者は企業の一方的なアピールよりも、リアルな声や活動に共感します。従業員もまた、ネームバリューや待遇だけでなく、社会貢献度や個人の尊重を重視するようになってきました。会社の魅力を伝える方法はお金だけではないのです。
この記事では、企業向けの移動ソリューションを提供する「バス旅ねっと」が、そのような時代の変化を踏まえ、企業ブランディングの基礎から企業理念の浸透プロセス、自社の事業リソースを活かした地域貢献企画のアイデアまでを、分かりやすく解説します。
Contents
企業ブランディングの基礎を知ろう
マーケティングや企画広報の業務に馴染みがないと、企業ブランディングは難しいではないかと感じがちですが、その考え方自体はとてもシンプルです。まずはその基本から理解していきましょう。
企業ブランディングとは?
企業ブランディングとは、顧客や社会に対して自社の「価値」や「理念」を伝え、信頼や共感を生み出すための活動全般を指します。企業の存在意義そのものを高めることで、事業の成長だけでなく、採用や社員のモチベーション向上にも繋がります。
混同されやすい言葉に「マーケティング」や「プロモーション」がありますが、これらは企業ブランディングの一部です。マーケティングは「商品が売れる仕組み」を作り、プロモーションは「商品を広く知ってもらうための宣伝活動」ですが、ブランディングは企業の根本的な価値を形作ること。これらの活動は、ブランディングという大きな土台の上で行われるものです。
企業ブランディングの事例
企業ブランディングの手法に正解はなく、企業の数だけ形があります。しかし、ブランディングを構成する要素を分解して考えると、取り組み方が見えてきます。まずは、以下の要素が自社にどう当てはまるか考えてみましょう。
| ロゴ・タグライン | 企業の顔となるシンボルや、理念を簡潔に表現した言葉。 【大手企業タグライン例】 ニトリ「お、ねだん以上。」 リクルート「まだ、ここにない、出会い。」 カルピス「カラダにピース。」 |
|---|---|
| 公式Webサイト | 企業の歴史、事業内容、社会貢献活動などを発信し、信頼性を高める。 |
| 商品・サービス | 顧客が直接触れるもので、品質やデザイン、使い心地などがブランドイメージを左右する。 |
| 店舗・オフィスデザイン | 企業のコンセプトを体現する空間で、顧客や従業員がブランドを体感する場。 |
| 社員の振る舞い | 企業の理念や価値観が浸透しているかを示す最も重要な要素。 |
| 広告・プロモーション | 企業メッセージを広く社会に伝え、認知度やイメージを形成する。 |
企業ブランディング成功の具体例をイメージしやすいように、大手有名企業の事例を挙げてみます。
無印良品
無印良品は、無駄な装飾をなくした「簡素」な美しさと「品質」を追求することで、「これでいい」という共感性の高いブランドイメージを確立しました。この哲学を社員全員が体現するため、同社では詳細な接客マニュアル「MUJIGRAM」を作成。接客の仕方から商品の陳列方法まで、すべての業務をマニュアル化することで、誰が担当しても同じ品質のサービスを提供できるようにしました。これにより、全国どの店舗でも一貫したブランド体験を顧客に提供でき、競合が提供する「派手なデザイン」や「流行」とは一線を画した、信頼性の高いブランドとしての地位を築くことに成功しました。
任天堂
任天堂は「娯楽に徹せよ。独創的であれ。」という、創業以来受け継がれてきた暗黙の哲学を大切にしています。この哲学は、固定されたルールではなく、社員が自律的に判断し、行動するための指針となっています。同社では、この哲学に基づき「任天堂に関わるすべての人を笑顔にする」という理念を掲げ、社員一人ひとりがそのためにどう貢献できるかを常に考えています。その結果、コアなゲーマー向けに性能を競う他社とは異なり、WiiやNintendo Switchのように、普段ゲームをしない人々も直感的に楽しめるような、独自のゲーム体験を創出。競合とは異なる「幅広い層に愛される娯楽」という市場を切り開くことに成功しています。
スターバックス
スターバックスは、美味しいコーヒーを提供するだけでなく、「サードプレイス(家庭でも職場でもない第三の居場所)」という心地よい体験価値を提供することで、他社と差別化を図りました。このコンセプトを実現するため、同社はまず従業員(パートナー)が働きやすい環境づくりに注力。アルバイトであっても3ヶ月に1度の評価・給与改定や、従業員満足度を測る調査を定期的に行うなど、手厚い福利厚生や教育制度でパートナーのエンゲージメント(会社への愛着)を高めています。その結果、パートナーは自社の価値観に共感し、高いホスピタリティを発揮。マニュアルを超えた丁寧な接客が生まれ、顧客との間に真の繋がりを築くことで、競合が提供する単なる「安価なコーヒー」ではなく、「特別な時間」を体験できるブランドとしての地位を確立しました。
このように、ブランディングは特別な手法ではなく、自社の理念や強みを明確にし、それを社内外に伝えていく活動そのものなのです。
企業ブランディングの形
この「企業ブランディング」という言葉自体、何をブランディングするかを示した1つの名称であり、企業の中で特定の人物にフォーカスした「パーソナルブランディング」や特定のサービスにフォーカスした「製品ブランディング」が存在します。その他にも企業ではなく特定の地域を訴求する「地域ブランディング」、どのようにブランディングするかの手法としての「デジタルブランディング」といった言葉もあります。
ですがブランディングで重要なのは、「誰を対象とするか」です。ここでは、ブランディングのターゲットを分類する3つのブランディングについて詳しく解説します。
アウターブランディングとは?
誰向けのブランディングかを考えた時に、真っ先に思い浮かぶのは会社の外側に向けた「アウターブランディング」でしょう。エクスターナルブランディングとも呼ばれます。
【対象者】顧客や取引先、社会全体
【目的】会社の認知度向上、信頼性やブランドイメージの構築、購買意欲の促進
大手企業がテレビCMや大規模な広告を打ち、ブランドイメージを世の中に浸透させているのは、このアウターブランディングの典型的な例です。しかし中小企業の場合は社員一人ひとりの日々の営業活動、つまり電話応対やメールでの言葉遣いなど、顧客との接点すべてがアウターブランディングの1部であると言えます。
インナーブランディングとは?
外側の反対は内側です。社内の全従業員に向けたブランディングが「インナーブランディング」です。
【対象者】全従業員
【目的】企業理念やビジョンの浸透、従業員のエンゲージメント向上、組織の一体感醸成
創業メンバーなどに企業理念が浸透していても、人が増えるにつれ徐々に企業理念は薄まるものです。社員が「何のために働いているか」を理解し、自社に誇りや愛着を持つことができれば、社員は自律的に行動するようになり、離職率の低下や生産性の向上といったメリットにも繋がります。これは、企業の安定的な成長に不可欠な土台作りと言えるでしょう。
採用ブランディングとは?
外側と内側どちらの側面も持つのが「採用ブランディング」です。
【対象者】新卒、中途の求職者
【目的】優秀な人材の獲得、採用活動におけるコスト削減、ミスマッチの防止
採用活動において「この会社で働きたい」と思ってもらうために、アウターブランディングとして企業の魅力を発信します。ですがどんなに魅力的な情報を外部に発信しても、実際の社内の文化(インナー)と乖離していれば入社後のミスマッチに繋がり、早期離職の原因となってしまいます。
すべてはインナーブランディングから
この3つのブランディングターゲットの内、重要なのは「インナーブランディング」です。莫大な広告費を使える大企業と違って、中小企業では特にこの影響が大きいでしょう。みなさんも飲食店などを選ぶ時、チェーン店であれば従業員の対応が多少悪くても一定の企業イメージをキープできるものの、個人店では従業員の対応1つでその店のイメージが決まってしまったという経験はありませんか?
社員一人ひとりが「自社は良い会社だ」と心から思える会社でなければ、どんなに外向きに良いアピールをしても、それは上辺だけの一時的なものにしかなりません。誇りを持った社員の行動や言葉こそが、何よりも説得力のあるアウターブランディングとなり、その社員の姿を見て「この人たちと一緒に働きたい」と感じた求職者が集まってくるのです。ブランドの宣伝大使である「ブランドアンバサダー」のイメージはSNSで活躍するインフルエンサーかもしれませんが、本当に強力なブランドアンバサダーは、他でもない自社の社員であると言えるでしょう。
インナーブランディングの形
企業ブランディングの第1歩はインナーブランディングであることがわかったところで、その実現手段について詳しく見ていきましょう。
インナーブランディングの基本
社内に向けて企業理念を浸透させるためには段階があります。まずは理念を形にしてからそれを内部から外部に伝播させていきましょう。特別な業務として浸透させるのではなく、日常のビジネスシーンの根底に常に流れる川のように伝わっていることが理想です。
| 1.理念の明確化 | まずパーパス(企業の存在意義)やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を再定義し、会社の目指す方向性を言語化します。この明確さが肝です。 | ・タグライン(価値フレーズ) ・クレドカード(信条カード) |
|---|---|---|
| 2.理念の共有 | 定義した企業理念は、会社の最新情報や社員の活躍事例とともに、組織全体に共有します。 | ・社内SNS ・社内報 ・全社集会 |
| 3.個人への浸透 | 業務を通じて、社員同士や上司・部下間の相互理解を深めます。価値観の押し付けではない、双方向のコミュニケーションが重要です。 | ・1on1ミーティング ・メンター制度 ・チームビルディング |
| 4.理念の実践 | 企業理念を日々の業務にどのように反映させるか、上司からの指示ではなく社員各自が自然に考えられることが理想です。 | ・マニュアルの見直し ・ケーススタディ ・エピソード共有 |
| 5.理念の定着 | 評価制度などに理念を反映させるとともに、業務だけに追われない労働環境整備を整備することで、理念は文化として定着します。 | ・バリュー評価 ・ボランティア休暇制度 ・フレックスタイム制度 |
| 6.理念の拡張 | 社外活動にまで理念が拡張されると、社員は個ではなく会社の一員として、自社の社会的意義を肌で感じるようになります。 | ・業界標準策定への参画 ・地域貢献活動 ・社会貢献活動 |
| 7.浸透サイクル | 企業理念が浸透すると、社員の帰属意識は高まり、業務の隅々にまで理念が行き渡ります。それに触れた求職者や消費者は、自社のファンになっていくでしょう。 | ・離職率低下 ・求職者増加 ・顧客増加 |
陥りがちなインナーブランディング失敗例
企業理念を体現する環境を整え、浸透サイクルに乗せることができれば、採用やアウターブランディングにも良い影響を与えることはイメージできたと思いますが、インナーブランディングは往々にして社内だけで完結し、成果が見えにくいという失敗に陥りがちです。ここではよくある失敗例をいくつか紹介します。
- 理念が抽象的で伝わらない
「顧客第一主義」「イノベーションの推進」など、抽象的な言葉で理念を終わらせてしまうと、社員は日々の業務と結びつけて考えることができません。結果として、理念は「ただのスローガン」となり、形骸化してしまいます。 - 上司が理念を『建前』と捉えている
トップが掲げる理念と、現場での経営判断や管理職の言動が一致していない場合、社員の会社に対する不信感に繋がり、理念浸透はうまくいきません。「言っていることとやっていることが違う」というギャップは、インナーブランディングを最も阻害する要因の一つです。 - 一方的な『押し付け』になってしまう
社内報や朝礼での理念発表など、会社から社員への一方的な情報伝達だけで終わってしまうと、「やらされ感」が生まれ、社員の主体的な行動には繋がりません。双方向の対話がなければ、理念は「自分事」として捉えられません。 - 活動そのものが目的化してしまう
クレドカードの配布や社内イベントの実施など、理念を浸透させるための活動が、いつの間にかそれ自体がゴールになってしまうケースです。本来の目的である社員の行動変容や会社の文化定着まで至らず、表面的な取り組みで終わってしまいます。
いずれの失敗例も、企業理念の明確化と共有の先にある双方向の浸透からうまく進めていませんね。このような失敗を避けるためには、理念を「言葉」で終わらせるのではなく、社員が自分事として捉え実践できる仕組みが必要なことがわかります。
インナーブランディングを成功させる3つの要素

大手企業の成功事例は遠い存在のように感じますが、現在の大手企業の多くは、小さな事業から始まりました。つまり、大企業だから成功したのではなく、成功したから大企業になれたのです。中小企業も、インナーブランディングから一歩ずつ進めていきましょう。
ここで解説する成功のための3つの要素とは、前章の「インナーブランディングの基本」で理念の明確化と理念の共有の次のフェーズにあった、個人への浸透・理念の実践・理念の定着の3つのことです。それぞれに具体例を挙げて詳しく見ていきましょう。
社員個人間での理念浸透
理念をトップダウンで一方的に伝えるだけでは、社員の心には響きません。理念を自分事として捉えてもらうためには、日々のコミュニケーションの中で、社員が自ら考え、語り合う双方向の対話が不可欠です。
上司と部下のコミュニケーション
理念を「自分事」として捉えてもらうためには、上司と部下の間に信頼関係を築き、双方向の対話を行うことが不可欠です。部下のキャリアプランや業務の悩みを上司が聞き、理念と結びつけることで、理念が日々の仕事の指針となります。
| 1on1ミーティング | 業務の進捗だけでなく、部下の成長や課題、キャリアについて定期的に話す1対1の対話です。 この場で部下は仕事の悩みや価値観を語り、上司はそれを理念と結びつけることで、理念が日々の仕事の指針となります。 |
|---|---|
| 人事評価面談 | 成果や行動について上司が評価を伝え、部下とすり合わせを行う面談です。 理念に沿った行動が評価の対象となることを明確に示し、理念の重要性を社員に伝えます。 |
| 目標設定面談 | 個人の業務目標や行動目標を、上司と一緒に設定する面談です。 個人の目標を会社の理念とどう結びつけるかを話し合い、理念を「自分事」として捉えるきっかけを作ります。 |
先輩と後輩のコミュニケーション
上司とは異なる立場である先輩・後輩間のコミュニケーションは、理念をより実践的なレベルで浸透させます。経験豊富な先輩が、後輩の疑問や不安に寄り添いながら、理念に基づいた行動を伝えていくことで、組織全体の一体感と文化が育まれます。
| キャリアインタビュー | 後輩が先輩に対し、キャリアパスや仕事のやりがい、大切にしている価値観などを質問し、話を聞く機会です。 先輩の実体験から理念をどう業務に活かすかを知る一方で、後輩の素朴な疑問や価値観が先輩の理念への理解を深めるきっかけにもなります。 |
|---|---|
| バディ制度 | 入社間もない新入社員が組織に早く適応できるよう、年齢の近い先輩社員がサポートする制度です。 日常の些細な疑問や社内の雰囲気を気軽に相談できる関係性を通じて、先輩は後輩の視点に触れ、理念をより分かりやすく伝える対話が生まれます。 |
| メンター制度 | 経験豊富な先輩社員が、若手社員のキャリア形成や精神的な成長を支援する制度です。 長期的な対話を通じて、先輩は後輩の成長を促すと同時に、後輩の持つ新しい価値観や視点から学びを得る双方向のサイクルが生まれます。 |
部署内のコミュニケーション
企業理念を実務に浸透させるためには、まずは最も身近な部署内のコミュニケーションが鍵となります。チームメンバー間で理念を共有し、日々の業務にどう活かすかを話し合うことで、理念が「自分事」となり、部署としての一体感が生まれます。
| 定例ミーティング | チームや部署内の情報共有や業務連携を目的として、定期的に開催される会議です。 業務の進捗報告だけでなく、理念に沿った成功事例や、課題をどう理念に基づいて解決するかを議論する場にすることで、理念が日々の仕事の判断基準として定着します。 |
|---|---|
| ブレインストーミング | 部署内のメンバーが集まり、特定のテーマや課題に対し、自由な発想で意見を出し合う会議手法です。 理念を「思考の軸」として活用することで、メンバーのアイデアに一貫性が生まれ、理念に基づいた新しいサービスや改善策が生まれやすくなります。 |
| チームビルディング | メンバー同士の親睦を深め、チームとしての一体感を高めることを目的とした活動です。 共通の目標に取り組むアクティビティなどを通じて、メンバー間の信頼関係が構築され、理念を共有する仲間としての絆を深めることができます。 |
業務内での理念実践
あらゆる社員間のコミュニケーションの中で企業理念を意識していくと、それが実務の細部へ徐々に反映されていきます。理念の実践を特別な行動とせず、日々の業務で社員一人ひとりが考え、自然な行動につながることこそが、強いブランド力を築く基盤となります。ここが不確かなまま先へ進んでも、机上の空論感は拭えませんので注意しましょう。
通常業務への組み込み
企業理念を「特別なもの」ではなく「当たり前のもの」にするためには、日々の業務フローの中に理念を組み込むことが不可欠です。稟議書や企画書、日報など、業務の要所要所で理念を意識する仕組みを作ることで、社員は自然と理念に基づいた判断や行動ができるようになります。
| 顧客対応マニュアル見直し | 問い合わせ対応や来客応対など、顧客と直接接する業務マニュアルに理念を反映させることです。 社員は理念に基づいた言葉遣いや応対方針を具体的に理解し、顧客に一貫したブランド体験を提供できます。 |
|---|---|
| 企画書・稟議書の確認項目 | 新規プロジェクトの企画書などに、企業理念との関連性を記述する項目を追加する制度です。 これにより、社員は提案段階から理念との整合性を意識するようになり、理念を事業活動の軸として捉える習慣が身につきます。 |
| 社内会議の進行ルール | 建設的な議論を促すためのルールや、多様な意見を尊重するためのルールを設けることです。 理念を「思考の軸」として会議を進めることで、メンバーは当事者意識を持って議論に参加し、より良い意思決定に繋がります。 |
問題へのアプローチ
顧客からのクレームや業務で発生した問題は、理念を「判断基準」として活用する絶好の機会です。上司や先輩の指示を待つのではなく、社員一人ひとりが理念に立ち返って自律的に考え、行動できる文化を醸成することが、組織全体の成長を促します。
| 業務改善チーム | 業務フローやサービスの弱点を、部署を越えて解決するチームを設置する制度です。 理念を共通の物差しとして課題解決に取り組むことで、部署間の連携が強まり、全社的な視点が育まれます。 |
|---|---|
| 理念ケーススタディ | 自社の成功・失敗事例を題材に、「理念に基づくとどう解決すべきか」を議論するワークショップです。 社員は理念をただの言葉で終わらせず、具体的な判断基準として活用する思考力を養います。 |
| クレーム対応ロールプレイング | 顧客からのクレーム対応やトラブル発生時のシチュエーションを想定し、理念に沿った言動を練習する機会です。 マニュアルにない状況でも理念に立ち返って自律的に判断し、行動できる能力を養います。 |
成功体験の共有
理念を体現した行動が評価され、称賛される仕組みは、社員のモチベーションを向上させ、理念浸透を加速させます。成功事例を社内全体で共有することで、「理念を実践すると良いことがある」というポジティブな連鎖を生み出します。
| 社員間サンクスカード | 理念に沿った行動をしてくれた同僚に対し、感謝の気持ちをメッセージにして送る制度です。 社員同士がお互いの良い行動を認め合う文化が醸成され、理念が日常のコミュニケーションに溶け込みます。 |
|---|---|
| 部署ごとの事例プレゼン会 | 部署内で共有された理念の実践事例を、全社にプレゼン形式で発表する機会です。 部署ごとの成功体験が可視化され、他の部署の社員が理念を自分事として捉えるきっかけになります。 |
| バリューアンバサダー制度 | 理念やバリューを深く体現している社員を「アンバサダー」として認定し、その成功体験やナレッジを社内に共有してもらう制度です。 認定された社員は、理念に関するワークショップの講師を務めたり、新入社員のメンターになったりすることで、理念浸透の旗振り役となります。 |
理念を定着させる環境づくり
理念の実践や拡張を単発で終わらせず、組織の文化として定着させるためには、それを支え、後押しする制度や仕組みが必要です。社員が安心して行動できる土台を整えましょう。
理念に基づいた人事評価制度
社員の評価する項目に、スキルや成果だけでなく、理念に沿った行動や価値観(バリュー)を組み込むことで、社員は「何が正解か」を具体的に理解できるようになります。短期的な成果だけでなく、中長期的な視点から理念に基づいた行動が称賛されるため、社員の主体性や創造性を引き出すことができるでしょう。
| 行動評価制度 | 理念に沿った「顧客への誠実な対応」「チームへの貢献」などの具体的な行動を評価項目に設定し、評価に反映させる制度です。 |
|---|---|
| 多面評価(360度評価) | 上司だけでなく、同僚や部下など、多角的な視点から理念を体現した行動を評価する制度です。理念の実践が正当に評価されやすくなります。 |
| バリューボーナス制度 | 理念やバリューを体現した社員に対し、特別なボーナスを支給する制度です。 理念を実践することの金銭的なメリットを明確にし、モチベーション向上を促します。 |
個人の業務外活動を支援する制度
理念を深く浸透させるためには、社員個人の成長も不可欠です。そのために社員が自律的に学び、新たな視点を獲得するチャンスは会社が積極的に支援しましょう。成長した社員によって、社内外での理念体現が広がるだけでなく、社員自身の会社への帰属意識やエンゲージメントを高めることもできます。
| 自己啓発支援制度 | 会社の理念に沿った資格取得や研修参加などを支援する制度です。 個人の成長と企業の目標を結びつけ、エンゲージメント向上に貢献します。 |
|---|---|
| 書籍購入補助制度 | 業務に必要な書籍や資料の購入費用を会社が補助する制度です。 社員の自主的な学習を促し、新しい知識や技術の習得を支援します。 |
| ボランティア休暇制度 | 理念に沿った社会貢献活動に参加する際、有給休暇とは別に休暇を付与する制度です。 社員は会社を代表して社会貢献に取り組むことができ、理念をより深く体感します。 |
柔軟な働き方ができる勤務形態
どんなに立派な理念を掲げても、社員が厳しい労働環境下にあっては、日々の業務に追われるだけになっていまいます。社員1人1人が業務の中で理念に立ち返る余裕を生むためには、時間的・精神的なゆとりを生む柔軟な勤務形態が必要です。またワークライフバランスの向上は、社員自身も安心して長く働ける土台にもなるでしょう。
| フルフレックスタイム制度 | 始業・終業時間を自由に設定できる制度です。 社員は最も集中できる時間帯に業務を割り当てることができ、生産性の向上に繋がります。 |
|---|---|
| リモートワーク制度 | 場所に縛られずに働ける制度です。 通勤時間の削減や、ライフスタイルに合わせた働き方が可能になり、社員のエンゲージメント向上に貢献します。 |
| 短時間勤務制度 | 所定労働時間よりも短い時間で勤務できる制度です。 育児や介護など、社員の個人的な事情に配慮することで、離職を防ぎ、多様な人材の確保に繋がります。 |
社員のエンゲージメントを高める社外活動

インナーブランディングの浸透・実践・定着という社内での流れができたら、次は社外へと広げる理念の拡張フェーズに進みましょう。企業理念が自社や自身の日々の業務内だけでなく、自社の属する業界や地域、さらには社会全体に役立つことを実感する体験が積み重なると、「この仕事に携わって良かった」と仕事への意義を強く感じるようになります。このようなエンゲージメントの高まりは周囲にも伝播し、社外活動を通じて触れ合った学生や子どもたちにも良い影響を与えるでしょう。企業イベントへの参加をきっかけにその会社に就職したという話はそんな良い事例ですね。
業界に役立つ社外活動
自社の利益を越えた業界全体の発展に貢献する活動は、社内から1つ外に向いた理念の体現の場となります。自社の専門性や知見を活かし、業界の技術標準策定に参画したり、業界の将来を担う学生向けの講座を開催したりすることは、社員のプロ意識を高めるため、日々の業務のモチベーションアップという良い循環につながるでしょう。
| 業種 | 活用リソース | アイデア |
|---|---|---|
| IT企業 | プログラミングの技術 | 業界内の技術者向けに、 最新技術に関する勉強会やワークショップを開催する。 |
| 建設会社 | 専門的なノウハウ | 業界の技術者向けに、 最新の安全基準や工法に関するセミナーを開催する。 |
| 製造業 | 自社製品 | 自社製品のノウハウを活かし、 新興メーカーの技術指導やコンサルティングを行う。 |
| 清掃会社 | 専門的なノウハウ | 業界団体と協力し、 清掃技術の標準化や資格制度の策定に貢献する。 |
| 飲食店 | 料理のノウハウ | 業界の若手料理人向けに、 レシピ開発や店舗運営に関する講座を開催する。 |
| サービス業 | 接客のプロ | 業界の交流会で、 顧客体験を向上させる接客ノウハウの講演を行う。 |
| 運送業 | 運搬のノウハウ | 同業他社と連携し、 効率的な配送網を構築する共同プロジェクトを立ち上げる。 |
| 観光業 | ツアー企画のノウハウ | 業界内の事業者向けに、 新しい観光コンテンツの企画ワークショップを主催する。 |
社会に役立つ社外活動
企業が事業活動を行う地域社会は身近な社会貢献の場であり、さらに大きな社会全体の課題解決につなげることもできます。地域のお祭りへの参加や清掃活動などを通じた地域住民とのふれあいだけでなく、自社の専門性やスキルを活かした社会貢献ができれば、さらなる社員のエンゲージメント向上が期待できるでしょう。
| 業種 | 活用リソース | アイデア |
|---|---|---|
| IT企業 | プログラミングの技術 | 地元の子ども向けに、 プログラミング教室を開催する。 |
| 建設会社 | 専門的なノウハウ | 地域住民向けに、 DIY教室や空き家改修プロジェクトに企画する。 |
| 製造業 | 自社製品 | 地域のお祭りやイベントで、 自社製品を使った体験ブースを出展する。 |
| 清掃会社 | 専門的なノウハウ | 公園や公共施設の清掃ボランティアを行い、 参加者に清掃方法を指導する。 |
| 飲食業 | 料理のノウハウ | 地域住民向けに、 地元の食材を使った料理教室を開催する。 |
| サービス業 | 接客のプロ | 高齢者施設を訪問し、 傾聴ボランティアや交流イベントを実施する。 |
| 運送業 | 運搬のノウハウ | 地域の災害訓練に協力し、 物資の運搬を支援する。 |
| 観光業 | ツアー企画のノウハウ | 地元の魅力を再発見のための、 スタンプラリーやウォーキングイベントを企画する。 |
社外活動の成功を支える計画準備
業界や社会に貢献するための社外活動には、このように様々な企画を考えることができますが、それを計画実行するには多くの準備が必要となります。普段の業務とは異なるプロジェクトであるため、段取りを間違えると失敗につながりかねません。ここでは企画を成功に導くために押さえておくべきポイント3つについて解説します。
予算とリソースの確保
どんなに素晴らしい企画も、実行するための予算や人員がなければ絵に描いた餅です。まずは、活動にかかる費用(会場費、資材費、参加者への謝礼など)を算出し、必要なリソースを明確にしましょう。特に普段の業務とは別に社員が活動に参加するため、どれくらいのマンパワーを充てられるか事前に確認し、現実的な計画を立てることが成功の鍵となります。
協力者・関係者との連携
社外活動は自社だけで完結するものではありません。活動の規模によっては、自治体や地域のNPO、業界団体、地域住民など、多くの関係者と協力する必要があります。活動の目的やメリットを丁寧に説明し、信頼関係を築くことで、単なる「場所の提供」や「人員の協力」を超えた、より深い共創関係が生まれるでしょう。
主催者や参加者の移動方法の確保
企画の実行で見落としがちなのが、企画の主催側となる自社スタッフや協力関係者、企画への参加者の移動方法の確保です。自社の周辺地域の近隣住人向け企画であれば、スタッフも参加者もアクセスしやすい会場となるケースが多いですが、自社と会場が離れている場合やゲストや関係者を招待する場合、主要駅と会場が離れている場合もあるでしょう。そのような場合は、各自の公共交通機関による移動ではなく、貸切バスのような専用の移動手段を手配しておくと、企画進行がスムーズです。
また貸切バスは車体とドライバーを占有チャーターできるサービスなので、利用者側の目的に合わせて自由な使い方ができます。シンプルな送迎はもちろん、ピストン運行によるシャトルバスとして利用することや、現地での控室や休憩室代わりに使うことも可能です。バス旅ねっとは法人様のご利用実績が豊富な貸切バス手配サービスですので、移動に関するお困り事はお気軽にご相談ください。
中小企業のブランディングまとめ
この記事ではインナーブランディングの基本から具体的な施策まで、多岐にわたる内容をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。インナーブランディングの奥の深さを感じていただいた反面、すべてを実行するのは大変だと不安になってしまった方もいるかもしれません。
でも大丈夫です。最も大切なのは「理念が浸透した自社の状態」というゴールのビジョンを明確に持つことです。それさえあれば部署単位での小さなプロジェクトや、既存の会議で理念について話す時間を設けるなど、できることからスモールスタートで問題ありません。そこから段階的にインナーブランディングを進めるにあたり、随時アンケートやヒアリングなど社員の反応や効果を得る手段を準備しておくと、長期的に取り組みやすくなります。
中小企業にとってインナーブランディングは、大企業に負けない強い組織をつくるための最も効果的な手段です。社員の成長と組織の一体感を醸成し、企業価値を高めるこの取り組みを、私たち「バス旅ねっと」も応援しています。理念体現を目的とした研修やイベントを企画する際は、移動ソリューションの専門家として、ぜひ私たちにご相談ください。専任担当者が企画から当日の運行までしっかりサポートさせていただきます。具体的なプランが決まられている場合は、お見積りフォームからのお問い合わせがスムーズです。