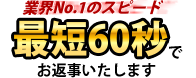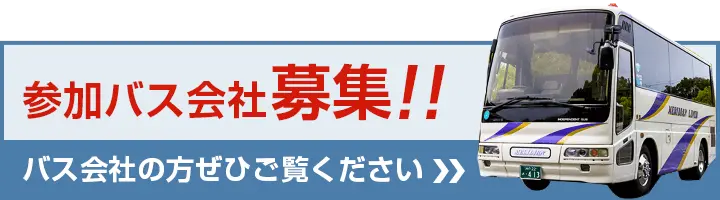夏イベントは活気に満ち、参加者の笑顔が輝く楽しい1日となるはずですが、イベントを主催する立場である担当者の方々には、毎年同じ悩みがつきまとうのではないでしょうか。それは高温多湿な環境下で避けられない「熱中症リスク」への対策と、その重い責任です。2024年4月から気象庁と環境省によって熱中症特別警戒アラートの運用が始まったように、その危険性は年々増しています。
この記事は、イベント送迎などで利用されることの多い貸切バス手配サービスの「バス旅ねっと」が、イベントにおける熱中症対策について、必要な情報を網羅的に解説しています。イベント担当者様の「万が一の事態があったらどうしよう」という不安を、安心に変える事前準備のためにお役立てください。
Contents
まずは熱中症の基本を知ろう

夏のイベントを安全に運営する上で、熱中症対策は避けて通れません。しかし、「熱中症」という言葉は知っていても、その原因や症状、予防策までの知識が漠然としたままでは「本当にこれで大丈夫だろうか?」と疑問が残ってしまいますよね。
イベント現場で熱中症による体調不良者を出さないためには、まず熱中症がどのようなものかを正しく理解することが第一歩です。まずはこの基本をわかりやすく解説していきます。
熱中症での救急搬送者数の増加
2025年は梅雨が極端に短く、6月から真夏並みの暑さとなりました。暑さに体が慣れる「暑熱順化」の前に起きた気温の急上昇のせいか、6月に熱中症で救急搬送された人数は17,229名を記録しました。暑さに慣れていく7月からは39,375名と例年並みに落ち着きましたが、8月末でも全国各地で猛暑日を記録するなど、今年は異例の暑さはまだまだ長引きそうです。
| 計測月 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 3,655 | 2,799 | 2,614 |
| 6月 | 7,235 | 7,275 | 17,229 |
| 7月 | 36,549 | 43,195 | 39,375 |
| 8月 | 34,835 | 32,806 | — |
| 9月 | 9,193 | 11,503 | — |
| 合計 | 91,467 | 97,578 | — |
そもそも熱中症とは?
熱中症とは高温多湿な環境下で体の体温調節機能が破綻し、体内に熱がこもることで起こる、様々な体調不良の総称です。昔は日射病や熱射病という言葉がよく使われていましたが、2000年から日本神経救急学会によって「熱中症」という言葉に統一されました。それによって熱によっておきる体調不良は、日射しに直接さらされる屋外だけでなく、屋内でも起きる危険性があることが認知されていきました。
メカニズムと危険性
なぜ人はこんなにも熱によって体調を崩してしまうのか、熱中症のメカニズムを見ていきましょう。
人間の体は、汗をかくことで体温を下げようとします。しかし気温や湿度が高い環境では汗が蒸発しにくくなり、体からの熱放出が追いつかなくなります。すると体内に熱がどんどん蓄積され、体の深部体温が異常に上昇してしまうのです。同時に大量の汗と共に水分や塩分(電解質)が失われ、脱水症状や電解質バランスの崩れが進行します。
この状態が続くと、臓器への血流が悪くなったり、神経機能に障害が出たりすることで、めまいや吐き気、頭痛といった症状から始まり、意識障害やけいれんへと重症化する危険性があります。最悪の場合、命に関わる非常に危険な状態に陥ることもあるため、「ただの夏バテだろう」と軽く見てはいけません。熱中症は、体温調節機能が壊れていく、緊急性の高い状態だと認識することが重要です。
もしかして熱中症?症状チェックリスト
イベントに参加したり仕事をしていると、「なんだかおかしいな…」と感じても、それが熱中症なのか、ただの疲れなのか、判断に迷うことは少なくありません。特に多忙なイベント現場では、小さな異変を見過ごしてしまいがちです。しかし、熱中症は早期発見・早期対応が命を救います。
こちらに、熱中症の初期症状から重症度に応じた具体的な症状をチェックリスト形式でご紹介しますので、参加者やスタッフの体調変化にいち早く気づき、適切な対処へと繋げるためにご活用ください。
特に中度以上の症状は命に関わる可能性があるため、直ちに医療機関への連絡や搬送を検討してください。
| 重症度 | 対応 | 症状 |
|---|---|---|
| I度(軽症) | 現場での応急処置で対応できる状態 | ▢ めまいや立ちくらみ ▢ 大量の汗、または汗が出ない ▢ 手足やふくらはぎなど筋肉が攣る ▢ 体のだるさ、倦怠感 ▢ 頭痛、吐き気(胃のむかつき) ▢ 判断力や集中力の低下 |
| II度(中等症) | 病院への搬送を必要とする状態 | ▢ 38℃以上の体温 ▢ 呼びかけへの反応が鈍い ▢ 意識が朦朧としている ▢ 全身の痙攣(筋肉の引きつり) ▢ 吐き気・嘔吐 ▢ 頭痛が続く、ズキズキする |
| III度(重症) | 入院して集中治療の必要性のある状態 | ▢ 呼びかけに反応しない ▢ 意識がない(昏睡状態) ▢ 全身の痙攣が続く ▢ 体温が異常に高い(40℃以上) ▢ まっすぐ歩けない(運動失調) ▢ 立てないほどの脱力感 |
熱中症リスクを高める具体的な条件とは?
では実際にどんな環境下で熱中症が起こりやすいのか、その条件について見ていきましょう。熱中症は単に「暑いから」という理由だけで起きるわけではありません。実は、特定の「条件」が複数重なることで、そのリスクは格段に高まります。これらの条件を事前に把握しコントロールすることで、イベントの安全性を飛躍的に高めることが可能です。
環境に関する条件
- 高い気温
日中の最高気温が高いのはもちろんですが、夜間の気温が下がりにくい(熱帯夜)状況も、体が休まらずリスクを高めます。特に、前日まで涼しかった日が急に暑くなるような急激な気温上昇も、体が暑さに慣れていないため熱中症のリスクを高めます。 - 高い湿度
湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、体からの熱の放出が妨げられます。日本の夏は特に湿度が高いため、注意が必要です。 - 日差し(輻射熱)
直射日光だけでなく、地面や建物からの照り返し(輻射熱)も体感温度を大きく上昇させます。アスファルトの照り返しは特に危険です。 - 風がない(無風)
風がない場所では、体表面の熱がこもりやすく、汗の蒸発も促進されにくいため、熱中症リスクが高まります。 - 閉鎖された空間
屋内でも風通しが悪く、冷房が効かない体育館やテント内などは、屋外以上に熱中症のリスクが高まることがあります。
身体に関する条件
- 脱水状態
水分補給が不足していると、汗をかけなくなり体温が上昇しやすくなります。喉の渇きを感じた時にはすでに軽度の脱水状態です。 - 睡眠不足や疲労
前日の睡眠不足や肉体的な疲労が蓄積していると、体の体温調節機能が低下し、熱中症になりやすくなります。 - 体調不良
風邪、下痢、二日酔いなどで体調を崩している時は、いつも以上に熱中症になりやすい状態です。 - 基礎疾患
高血圧、糖尿病、心臓病などの持病がある方、あるいは高齢者や乳幼児は、体温調節機能が十分に働かないことがあり、熱中症のリスクが高い傾向にあります。 - 厚着、通気性の悪い服装
熱がこもりやすい服装は、体温の上昇を助長します。
行動に関する条件
- 激しい運動
大量の熱を発生させる激しい運動は、短時間でも体温を急上昇させ、熱中症のリスクを大幅に高めます。普段から運動習慣がない人が急に激しい運動をするなど、慣れない運動も体への負担が大きく、熱中症リスクを高めます。 - 長時間の屋外活動
日中の一番暑い時間帯(14時前後)に長時間屋外で活動することは、熱中症の大きな要因となります。 - 水分・塩分補給不足
活動中にこまめな水分・塩分補給を怠ると、脱水が進行し、リスクが高まります。また会場が混雑していて、トイレや給水所にアクセスしにくい水分補給しにくい状況も、無意識のうちに水分摂取を控えさせてしまい、リスクを高める要因となります。 - 休憩不足
定期的な休憩を取らずに活動を続けると、体が熱を放出しきれず、熱が蓄積されていきます。
これらの条件は単独では大きなリスクにならなくとも、実際には複数重なり合って発生するため、リスクは指数関数的に高まります。イベント運営者の立場では、参加者個人の行動を必要以上に制限することはできませんが、注意喚起や会場の事前対策をするための情報として理解しておきましょう。
熱中症予防になる飲み物と危険な飲み物
夏のイベントで「喉が渇いたから、とりあえず何か飲もう」という行動が、かえって熱中症のリスクを高めることがあるのをご存知でしょうか。「どのような飲み物を提供し、推奨すべきか」は、イベントを主催する側として慎重に判断したい点です。熱中症予防に効果的な飲み物と、逆に避けるべき飲み物には明確な違いがあります。ここでは、イベントでの適切な水分補給を促すために「選ぶべき飲み物」と「避けるべき飲み物」を具体的に解説します。
【OK】電解質も一緒に取れる飲み物
熱中症を効果的に予防するには、水分だけでなく、汗と共に失われる電解質(塩分など)も補給できる飲み物の選択が非常に重要です。特に大量に汗をかく状況では、水だけを摂取すると体内の塩分濃度が薄まり、「低ナトリウム血症」を引き起こすリスクがあるため、注意が必要です。
- スポーツドリンク
汗で失われる水分と電解質をバランス良く補給できます。ただし糖分が多い飲料もあるため、過剰摂取には注意が必要です。活動量に応じて薄めて飲んだり、糖分控えめのものを選びましょう。 - 経口補水液
スポーツドリンクよりも電解質(特に塩分)の濃度が高く、体への吸収が速いのが特徴です。すでに脱水症状の兆候が見られる場合や、大量発汗が予想される過酷な状況下で有効なため救護所などへの常備も推奨されます。ただし普段の水分補給には適していませんので注意しましょう。 - 麦茶
利尿作用のあるカフェインを含んでいないため、体内の水分を効率的に保持する日常的な水分補給に適しています。ミネラルも少量含まれていますが、大量に汗をかいたあとの塩分補給には、塩分タブレットなどとの併用が良いでしょう。
【NG】利尿作用のある飲み物
熱中症予防として不適切、あるいは摂取量に注意が必要な飲み物もあります。これらは体内の水分を排出する作用があるため、かえって脱水状態を招き、熱中症リスクを高める可能性があります。イベントでの提供や推奨には注意が必要です。
- アルコール飲料
ビールや酎ハイなどアルコールには強い利尿作用があり、飲酒量以上に体内の水分を排出させてしまいます。またアルコール分解過程で水分を消費し、体温も上昇させるため、脱水と熱中症のリスクが一気に高まります。 - カフェインを多く含む飲み物
コーヒー・紅茶・緑茶などに多く含まれるカフェインにも利尿作用があるため、過剰摂取は脱水につながる可能性があります。適量であれば問題ありませんが、真夏の炎天下での主な水分補給源にするのは避けるべきです。 - 糖分を多く含む清涼飲料水
炭酸飲料だけでなく果汁100%のジュースにも想像以上に多量の糖分が含まれています。糖分の多い飲料を飲んだあと、余計に喉が乾くことがありませんか?これは血糖値の急上昇を招いているためで、かえって脱水を促進したり、胃腸に負担をかけたりすることがあります。過剰な糖分摂取は、体のだるさにも繋がることがあるため注意が必要です。
イベント主催者はこれらの情報を理解した上で、参加者やスタッフの健康を守るための適切な飲み物選びと提供を心がけてください。特にイベント中のアルコール提供時は、水分補給も一緒にアナウンスするなど、注意喚起が必要です。
イベント運営者が準備すべき熱中症対策とは?
さてここからが本題です。暑いシーズンに開催を控えるイベント運営陣にとって、最も重要なミッションの一つが、参加者とスタッフ全員を熱中症から守ることではないでしょうか。「何から手をつければいいのか」「限られた予算と人員でどこまでできるのか」といった不安を抱えているかもしれません。しかし、適切な準備を怠ると、イベントの成功だけでなく、参加者の健康と安全に大きな影響を及ぼす可能性があります。ここでは、イベントを主催する側が事前に知っておくべき、そして確実に準備すべき熱中症対策の全体像を、あなたのイベント現場で実践できるよう、網羅的かつ具体的な視点から解説します。
WBGT測定器(熱中症計)の設置
イベント会場の熱中症対策において、WBGT測定器を使ったWBGT値の監視は、もはやイベントを主催する側の基本かつ常識となりつつあります。また2025年6月1日からは「WBGT値28度以上または気温31度以上かつ、連続して1時間以上で1日あたり4時間を超える作業」に従事させる場合は、企業側の熱中症対策が法律で義務付けられました(厚労省「職場における熱中症対策の強化について」)。
しかし、「具体的にどこにどう置けば、本当に正確なリスクを測れるのだろうか」と、その効果的な設置場所に頭を悩ませる方も少なくないかもしれません。ここでは、WBGT測定器の基本的な役割から、より正確なWBGT値を測定するための具体的な設置アドバイスまで、詳しく解説します。
WBGT測定器とは?
WBGT測定器がどのようなものか解説する前に、まずはWBGT値の定義を見てみましょう。
WBGT値とは?
暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)とは、人間の熱バランスに影響の大きい気温・湿度・輻射熱(ふくしゃねつ ※1 )の、3つを取り入れた温度の指標です。※2 熱中症の危険度を判断する数値として、環境省では平成18年から暑さ指数(WBGT)の情報を提供しています。暑さ指数(WBGT)は乾球温度計、湿球温度計、黒球温度計による計測値を使って計算されます。
※1 輻射熱とは、日射しを浴びたときに受ける熱や、地面、建物、人体などから出ている熱です。温度が高い物からはたくさん出ます。
引用元:環境省 熱中症予防情報サイト
※2 正確には、これら3つに加え、風(気流)も指標に影響します。
WBGTの数値によって運動レベルには下記の表のような指針があり、「熱中症特別警戒アラート」は翌日の暑さ指数(WBGT値)が35以上で発令されます。WBGT値35になる気温と湿度の組み合わせは多数ありますが、気温38度で湿度60%というレベルのため、2024年4月の運用開始以降まだ発令されていません。
「熱中症警戒アラート」はWBGT値33以上で発令されるため、暑い時期の天気予報ではすっかりお馴染みです。熱中症警戒アラートが発令される地域は年々拡大しており、北海道北見市では2025年7月24日に39℃が記録されるなど、北海道も対象エリアとなりました。2025年の夏は史上初となる北海道での40℃が観測されるかもしれませんね。

このように3種の熱中症のリスクを計測するための指標であるため、測定するための器具であるWBGT測定器(熱中症計)も、センサーによって気温と湿度を測り、黒球部分で輻射熱を測定することができます。
WBGT測定器の効果的な設置方法
WBGT測定器は参加者が多く活動する場所や、日当たりが強く風通しが悪いなど、特に熱中症リスクが高い地点を選んで設置しましょう。会場内に日向と日陰など環境が異なるエリアがある場合は、それぞれを代表する複数地点に設置するのが理想的です。
- 環境に合わせた設置と設定
屋外イベントでは、直射日光下の活動リスクを測る「日射あり」と、休憩場所など日陰の環境を測る「日射なし」の設定を使い分けましょう。屋内イベントでも、風通しが悪く熱がこもりやすい場所や、人が密集する場所ではWBGT測定器の活用を検討してください。冷房が効いていても、環境によっては熱中症リスクが高まる場合があります。 - 活動している人に合わせた高さに設置
WBGT測定器を設置する位置の高さは、活動している人の体感に合わせて調整することが重要です。一般的には、床上1.1m~1.5mの範囲で測定することが推奨されています。さらに小さな子どもが多く参加するイベントでは、身長の高さに合わせて0.5m程度にも設置を検討してください。地表面からの照り返しが子どもに与える影響は大きく、体感温度も高くなる傾向があるためです。 - 設置場所の周辺環境をチェック
正確なWBGT値を測定するためには、周辺環境から受ける影響のチェックが不可欠です。測定器自体が局所的に日差しを浴びたり、アスファルトからの強い照り返しを受けると、実際より高い数値が観測されることがあります。そのような影響を受けないように、測定器自体が影になるように設置したり、専用の遮光カバーを使いましょう。また発電機や調理器具、車のエンジンなど、熱を出す人工的な熱源からも、十分に距離を取ってください。
WBGT測定器の効果的な測定方法
WBGT値は時間と共に変化します。そのため、少なくとも30分~1時間ごとに測定し、その値を記録することで、会場のリスクがどのように変化しているかを把握できます。これにより、熱中症への注意喚起や休憩指示を出す適切なタイミングを客観的な数値に基づいて見極めることが可能です。
また測定する時は輻射熱を測る黒い球体部分を持たないように注意しましょう。
水分補給の計画は?

基礎知識の章で熱中症対策で重要なのは「水分補給」であることを見てきましたが、単に「水分を摂ってください」と呼びかけるだけでは不十分です。イベントの主催者として、参加者が「いつ」「どこで」「何を」「どれくらい」補給できるのかまで、事前に周到な計画を立て、適切な水分補給手段とルートを確保しておきましょう。
イベント参加時の推奨水分摂取量は?
水分補給計画を立てる上で、まず重要なのは必要水分量の把握です。熱中症対策の一般的な目安は、1回あたりコップ1杯(200ml~250ml)を1時間半~2時間おきなどの定期摂取です。イベントの環境や参加者の活動内容によって、推奨される水分摂取量は異なりますので、シーンごとのポイントは見ていきましょう。いずれのケースにおいても、喉が渇く前に定期的に飲むこと、汗をかいたら塩分も補給することが重要です。
- 屋内イベントの場合
冷房が効いている屋内でも、人が密集したり、空調で乾燥したりすることで脱水が進むことがあります。一般的な目安に沿って、定期的に水分摂取を促しましょう。給水ポイントはトイレに近い場所に設けるなど、気軽に補給できる環境が重要です。 - 屋外イベントの場合
屋外は発汗量が格段に増加しやすいため、屋内に比べより頻繁な水分補給が求められます。炎天下では特に、喉が渇く前にこまめに摂取することが重要です。日陰の休憩スペースや給水ポイントを確保し、冷えた飲み物を提供できるよう準備しましょう。 - 運動を伴うイベントの場合
スポーツ大会やライブイベントなど、発汗量の多い運動を伴う場合は、短時間で大量の水分と電解質が失われます。運動前には事前に水分を摂取し、運動中も1時間あたり500ml~1Lを目安に、15分~20分ごとに100ml~200mlずつ摂取するよう呼びかけましょう。水だけでなく、電解質を含むスポーツドリンクや経口補水液の活用が非常に有効です。給水ポイントを活動エリアの近くに複数設置するなど、迅速に補給できる体制を整えることが必須です。
イベントでの水分補給手段は?
水分補給が「いつ」「どれぐらい」必要かわかったところで、「どこで」「なにを」の部分を考えていきましょう。イベント主催者側は、参加者が安心して水分補給できるよう、複数の手段を確保しておくのが大切です。有料で飲料を購入できる場所から、主催者側が提供する無料の給水スポットまで、計画的に準備を進めましょう。
参加者が飲料を購入できるスポットの把握
商業施設などで喉が乾いた時に、自動販売機がどこにあるのか探した経験はありませんか?イベント会場で参加者が自分で飲み物を買おうと思った時の案内、無料の給水場所の設置ポイントの計画、どちらにおいても、自動販売機・売店・飲食店・出店ブースなどの位置把握は重要です。
- 会場マップへの記載
飲み物が購入できるスポットは会場マップに明記し、参加者が迷わずたどり着けるように案内しましょう。特に日差しが強く熱中症リスクが高いエリアや、人の流れが滞留するエリアの近くに、こうした購入場所があるかを確認しておくのが肝心です。 - ゴミ箱の設置
自動販売機や売店で飲料が売れるほど、ペットボトルや紙コップなどの空容器のゴミが増えます。イベントの規模によっては、既存のゴミ箱だけではすぐに溢れてしまう可能性があるので、臨時の大きなゴミ箱を複数設置したり、定期的な回収ルートを計画したりする必要があります。ゴミの放置は衛生面だけでなく、景観の悪化にもつながるので、十分な対策を講じましょう。
無料給水スポットの設置
特に熱中症のリスクが高いと懸念される環境下では、有料の飲料販売場所だけでなく、イベント主催者側で無料の給水スポットを設けることを検討してください。準備する水分量は、イベントの内容に合わせた1人あたりの水分摂取量目安と動員規模から計算し、緊急時の予備飲料なども確保しておくと良いでしょう。
給水スポットの例
- ウォーターサーバー
最も基本的な提供方法です。会場施設自体に備え付けの冷水機が無い場合は、ウォーターサーバーなどを設置し、使い捨て紙コップを十分に用意しましょう。参加者のマイボトルに給水できるボトル給水器も、サステナブルな取り組みとしておすすめです。 - 飲料メーカー協賛品
来場者への配布用として飲料を提供してもらえるイベント協賛スポンサーを、飲料メーカーで探すのも1つの方法です。小規模なイベントでも、会場の施設などに伝手がないか相談してみましょう。提供品・準備品いずれの場合も、ペットボトルなどを冷やすための氷を入れたクーラーボックスは必要です。
注意すべきこと
- 設置場所
給水スポットは既存の飲料購入スポットの間を埋めるように会場全体に分散させ、参加者が無理なく数分以内にたどり着けるよう配置しましょう。人の流れが多い場所や、休憩エリアの近く、日陰になる場所などが理想的です。 - 案内表示
混雑するイベント当日は、会場下見時の想定以上に案内表示が必要です。「給水所」「Free Water」などと大きく掲示するだけでなく、多言語対応も考慮しておきましょう。 - アナウンス
自ら給水スポットを探す人以外にも水分補給を意識してもらうために、「喉が渇く前にコップ一杯の水を」など定期的な会場アナウンスも大切です。巡回スタッフの声掛けや、のぼり旗・デジタルサイネージなどの活用も効果的です。 - 混雑時の列対策
無料給水スポットに長蛇の列ができると、かえって熱中症のリスクを高める可能性があります。混雑時の運用を想定し、複数の給水口を設けたり、給水スタッフを確保したり、効率的な動線を確保するなどの対策を講じましょう。
クールダウンスペースの作り方

定期的な水分補給への対策ができても、暑さに晒されたままでは熱中症対策は万全と言えません。夏のイベントでは参加者が一時的に暑さから逃れ、体を冷やせるクールダウンスペースの確保も不可欠です。ただ日陰を作るだけでなく、いかに効果的に体を冷やし、回復を促すか、予算や規模に応じた実践的なクールダウンスペースの作り方をご紹介します。
既存資源の活用ですぐできる方法
まずは特別な設備投資がなくとも、イベント会場の既存資源を活用できるクールダウンスペースの設け方です。アイデア次第ですぐに実践できますよ。
- 樹木や建物の配置を活かす
会場内の大きな樹木の下や、建物の陰になる場所は、自然な日陰を提供してくれる貴重なクールダウンスペースとなります。事前に会場を下見し、日中の太陽の動きに合わせてどこに影ができるかを把握しておきましょう。 - 屋内スペースの活用
会場に屋内施設(ホール・会議室・休憩所など)がある場合は、そこをクールダウンスペースとして開放しましょう。冷房が完備されている場所であれば、最も効果的なクールダウンが期待できます。冷房がない場合でも、窓を開けて風通しを良くしたり、扇風機を設置したりするだけでも効果があります。
手軽に購入できるアイテムでできる方法
次に初期費用を抑えつつ、既存資源だけでは不十分な場合に、市販の手軽なアイテムを導入してクールダウンスペースを強化する方法です。準備も比較的簡単なので、導入しやすいでしょう。
- 扇風機
電源が確保できる場所であれば、家庭用や業務用扇風機を複数設置するだけで、空気の循環を促し、体感温度を下げることができます。特に給水ポイントや休憩スペースと併用すると効果的です。 - 簡易設置型ミストシャワー
ホースに接続するだけで使える簡易的なミストシャワーは、手軽に涼感を演出できます。水の気化熱で周囲の温度を下げ、体感温度をクールダウンさせる効果があります。ただし、地面が濡れて滑りやすくなる可能性や、電子機器への影響に注意が必要です。 - タープやシェード
日差しを遮るタープやシェードは、設営が比較的簡単で、広範囲に日陰を作り出すことができます。UVカット機能のあるものを選び、風で飛ばされないようしっかりと固定しましょう。休憩用の椅子やベンチと組み合わせることで、より快適な空間になります。
レンタルや設備導入で万全を期す方法
大規模なイベントでは、専門業者からのレンタルや設備が必要な対策が求められます。これらは導入コストが高額ですが、その分確実な効果が期待できます。
- 大型テント: 設営に手間はかかりますが、広大な日陰空間を確保できる大型テントは、多数の参加者が同時にクールダウンできるスペースとなります。換気を考慮した設計のものを選びましょう。
- スポットクーラー: 特定のエリアを強力に冷やしたい場合に有効です。冷風をピンポイントで送ることができ、熱がこもりやすい場所や、体調不良者が発生した場合の緊急対応スペースなどで威力を発揮します。電源の確保と排熱処理の計画が重要です。
- ポンプ加圧型ミストシャワー: 簡易型よりも広範囲に均一なミストを噴霧でき、より高い冷却効果が期待できます。専門業者による設置が必要な場合が多いですが、大規模なクールダウンスペースを効果的に運用する上で非常に有効な手段となります。
これらの方法を組み合わせることで、イベントの規模や予算、会場の特性に応じた最適なクールダウンスペースを構築し、参加者とスタッフの安全を確保しましょう。
便利なクールダウンアイテムは?
最後にご紹介するのは、熱中症に効果的なクールダウンアイテムです。これらのアイテムは、参加者各自が持参する対策としても有効ですが、イベントを主催する側の対策として、参加者への無料配布や販売、スタッフへの積極的な支給を検討しましょう。
- 冷却ベストや空調服
体の深部体温上昇を抑えるのに非常に効果的なアイテムです。特に屋外や熱のこもりやすい場所で活動するスタッフには、支給しましょう。 - ネッククーラーや冷却タオル
首元や動脈が通る部分を冷やすことで、効率的にクールダウンできます。水に濡らして絞るだけで冷たくなるタイプや、繰り返し使えるタイプが便利です。参加者向けに会場内で販売・配布したり、スタッフ用には定期的に交換できる数を準備しておきましょう。 - 保冷剤や冷却パック
冷凍庫で凍らせるタイプの保冷剤は、時間の経過とともに冷却効果がなくなりますが、叩くと冷える瞬間冷却パックは使用したい時から冷却効果を得ることができます。緊急時のアイシングにも最適です。 - 冷感スプレーや冷却スプレー
ひんやりと冷たいメントールの清涼感が得られる冷感スプレーは、肌に直接使えるスプレーです。ガスを使用する急速冷却スプレーは服の上からしか使えませんが、熱中症対策にも効果的です。また希釈したハッカ油スプレーはタオルや帽子にかけると清涼感が得られるだけでなく、虫よけにもなります。 - 携帯用扇風機
手軽に持ち運べるポータブル扇風機を持っているという方は多いのではないでしょうか?スタッフ用に準備しておくのもおすすめです。 - うちわや扇子
直接的な冷却効果は低いものの、仰ぐことで風を作り出し、体感温度を下げることができます。ノベルティとして配布すれば、イベントの記念品にもなり、参加者の熱中症対策への意識を高めるきっかけにもなります。 - 冷たいおしぼり
給水所や休憩スペースで冷たいおしぼりを提供すると、首元や顔を拭くことでリフレッシュでき、体感温度も下がります。使い捨てタイプであれば衛生的です。
イベント運営者に必要な安全管理体制とは?

熱中症対策に有効な手段を見てきましたが、これらは単に場所や物を準備するだけでは不十分です。万全な安全管理体制や、「もしも」の事態に備えた周到な計画があって成り立つものです。特に大規模なイベントや、リスクの高い環境下での開催ではしっかり対策を講じておきましょう。ここでは、より専門的かつ包括的な安全管理体制について解説します。
イベント開催前の事前準備
熱中症対策を含むイベントの安全管理は、開催前から周到な準備を行うことが成功の鍵を握ります。本番で慌てないためにも、事前にしっかりと計画を立てておきましょう。
関係機関との連携と計画
イベントの安全を確保するには、主催者だけでなく、地域の関係機関との協力体制を築くことが不可欠です。事前に連携を取ることで、万が一の事態にも迅速かつスムーズに対応できるようになります。
まずは、イベントを管轄する消防署、警察署、および地方自治体に連絡を取り、イベントの概要と安全管理計画について共有しましょう。大規模なイベントの場合、イベント開催の届け出や許可申請の際に、熱中症対策を含む安全計画の提出が求められることもあります。特に、熱中症対策として設ける救護所の計画や、救急搬送ルートについて、消防署と事前に確認しておくことは非常に重要です。
また、近隣の医療機関との連携も欠かせません。多数の熱中症患者が発生した場合の受け入れ体制や、搬送に関する協力について、あらかじめ話し合っておきましょう。さらに、2024年から導入された『熱中症特別警戒アラート』が発令された際のイベント中止・延期の判断基準や、参加者への周知、緊急避難場所の確保といった対応方針についても、事前に策定し関係機関と共有しておくことが重要です。
事前に連携先を明確にしておくことで、当日の混乱を避け、迅速な救命活動に繋がります。
参加者に事前周知すべきことは?
イベントを安全に楽しんでもらうためには、主催者からの情報発信だけでなく、参加者自身にも熱中症対策への意識を高めてもらうのが不可欠です。開催前からしっかりと情報を届け、来場者の協力を促しましょう。
- イベント公式ウェブサイトやSNSで継続的に発信
イベント開催の数週間前から、公式サイトの目立つ場所や公式SNSで熱中症対策に関する注意喚起を継続的に行いましょう。水分補給の重要性、推奨される服装、持ち込み可能なアイテム、会場内の給水ポイントやクールダウンスペースの場所などを具体的に案内してください。 - チケットや入場時配布物にも記載
チケットの裏面、入場時に配布するパンフレット、会場マップなどにも、熱中症対策の注意点や緊急連絡先を簡潔に記載しましょう。視覚的に分かりやすいイラストやアイコンを活用すると、より多くの参加者に情報が伝わります。 - 当日までの気温・暑さ指数(WBGT値)予報を共有
イベント前日や当日に、予想される気温やWBGT値(暑さ指数)を共有し、どの程度の警戒が必要か参加者に伝えることが重要です。WBGT値35以上の「熱中症特別警戒アラート」発令時など、危険レベルが予想される場合は、イベント内容の変更や中止の可能性についても言及し、参加者が適切な判断を下せるように促す配慮も必要です。これは、主催者の責任範囲を明確にすることにもつながります。
イベント当日の運用と緊急対応
事前の準備がどれほど周到でも、イベント当日に効果的に運用し、万が一の事態に迅速に対応できる体制がなければ意味がありません。ここでは、熱中症対策における当日の運営と、緊急時における具体的な対応について解説します。
スタッフの役割分担と連携体制
イベント当日は、限られたスタッフで多くの参加者の安全を守る必要があります。そのためには、熱中症対策におけるスタッフの役割を明確にし、スムーズに連携できる体制を構築することが重要です。
- 熱中症対策担当者を明確にする
イベント全体の熱中症対策を統括する責任者を明確に定めましょう。この担当者は、WBGT値(暑さ指数)の計測・管理、水分補給やクールダウンスペースの運用状況確認、そして緊急時の判断・指示など、一貫した対策実行を担います。 - 巡回スタッフの配置と役割を明確にする
会場内を定期的に巡回し、参加者の様子に異変がないかを確認するスタッフを配置しましょう。体調不良者を発見した際の初期対応(声かけ、涼しい場所への誘導など)や、適切な部署への連絡方法を徹底的に訓練しておくことが重要です。 - 給水・救護スタッフとの連携を密にする
給水ポイントや救護所に配置されたスタッフは、自身の担当範囲だけでなく、体調不良者発見時の初期対応や、情報共有の連携フローを把握しておく必要があります。無線機や連絡アプリなどを活用し、リアルタイムでの情報共有ができる体制を整えましょう。 - スタッフ自身の体調管理も徹底する
スタッフ自身も、長時間にわたる活動で熱中症になるリスクがあります。雇用側として、スタッフの健康管理を徹底し、質の高いイベント運営の基盤を築きましょう。具体的には、イベント前に健康診断の受診を促し、体調不良者は無理をさせない体制を整えることが重要です。当日は、なるべく短時間で交代させ、日陰や冷房の効いた涼しい場所で積極的に休憩を取るよう徹底するとともに、定期的な水分補給を義務付け、冷却アイテムの支給も行いましょう。
緊急時の対応フローと訓練
事前の準備がどれだけ完璧でも、実際に熱中症の症状を訴える参加者が出た際に、スタッフが迷わず動けるかどうかが、その後の状況を大きく左右します。迅速かつ適切な対応のために、具体的なフローの確立と日頃からの訓練が不可欠です。
- 熱中症対応マニュアルの作成
熱中症の症状レベル(軽度、中度、重度)ごとに、具体的な応急処置の手順(涼しい場所への移動、衣類を緩める、体を冷やす、水分・塩分補給など)を詳細に記載したマニュアルを作成しましょう。救護所へ搬送すべきか、救急車を呼ぶべきかなど、スタッフが迷わず判断できる明確な基準を設けることも重要です。また、医療機関、救急隊、警察、イベント本部、責任者などの緊急連絡先を分かりやすくリスト化し、マニュアルに含めておくと安心です。 - スタッフへの研修とロールプレイングの実施
マニュアルは作成するだけでなく、実際にスタッフ全員が内容を理解し、実践できることが重要です。イベント開催前に、熱中症の基礎知識、症状の判断、応急措置、そして連絡フローについて徹底的な研修を行いましょう。可能であれば、実際の状況を想定したロールプレイング(模擬訓練)を実施し、スムーズな連携と対応ができるよう訓練を繰り返すことで、本番での対応力を高められます。 - 情報共有と記録の徹底
緊急事態発生時には、速やかに状況を共有し、対応内容を正確に記録することが重要です。いつ、どこで、どのような症状の参加者が出たのか、どのような対応を行い、最終的にどうなったかを記録に残すことで、今後のイベント運営における改善点を見つける貴重なデータとなります。
貸切バスがイベント会場で大活躍?

これまでイベント運営における熱中症対策の具体的な方法を詳しく見てきましたが、イベントのピストン送迎やスタッフ送迎に重宝される貸切バスが熱中症対策に活用できるのをご存知ですか?貸切バスはその名の通り、貸し切って占有使用できるため、移動中だけでなくイベント会場でのプライベート空間として活用することができるんです。ここでは、そんな貸切バスの賢い活用方法と、バス車内での熱中症対策についてご紹介します。
バス車内を休憩スポットとして活用
イベント会場によっては、十分なクールダウンスペースの確保が難しい場合があります。そんな時は、貸切バスの車内を一時的な休憩スポットとして活用する方法を検討してみてください。スタッフや出演者の休憩場所としても利用できますよ。
実際に2025年4月から開催されている大阪・関西万博では、クーラーのかかったEVバスが、会場内のクールダウンスペースの1つとして利用されることが決まりました。また万博会場には、人混みや騒音などの強い刺激に過敏な方が精神的なクールダウンを行なうための、個室暗所であるカームダウンスペースも用意されています。貸切バスはパブリックスペースとしてのクールダウンスポットとして利用するよりも、プライベートなカームダウンスペースとして活用する方が適しているかもしれませんね。
バス車内で注意する熱中症対策は?
貸切バスの車内はエアコンが効いていて快適に過ごせる一方で、移動中も油断はできません。バス特有の環境も考慮し、参加者が安全に移動できるよう以下の点に注意を促しましょう。
- エアコンの調整
バス車内は、乗車人数や外気温によって体感温度が大きく変わることがあります。乗務員と連携し、乗客が快適に感じるようエアコンの設定を適切に調整してもらうように依頼しましょう。一般的に、乗用車では25℃程度が快適な目安とされることが多いですが、寒すぎると感じる人もいるため、ブランケットなどの準備も有効です。乗客が多い場合は換気も重要です。 - 乗車前に水分補給を促す
バスに乗る前や乗車中は、必ず水分補給をするよう声かけをしましょう。特に外から暑い車内に入ると、体が追いつかず体調を崩す原因になることがあります。トイレに行きたくなるから水分補給を控えることがないように、トイレ休憩を挟んだ余裕のあるスケジュールにすることも大切です。 - 換気とリフレッシュ
休憩のために停車する際は、可能であればドアを開けて車内の空気を入れ替えましょう。また、休憩中にバスを降りて外の空気を吸い、軽いストレッチなどでリフレッシュすることも熱中症予防には効果的です。 - 体調不良者の早期発見
長時間移動をしていると、バス車内での体調不良者に気づきにくいこともあります。進行の担当者は乗車中も定期的に車内の様子を確認し、異変を感じる人がいないか目を配りましょう。
イベントにおける熱中症対策ガイドまとめ
夏のイベントを成功させるためには、徹底した熱中症対策が不可欠です。本ガイドでは、熱中症の基本的な知識からリスクの高い条件、効果的な水分補給の方法、クールダウンスペースの作り方、役立つアイテムの活用術、そして何よりも重要な安全管理体制の構築まで、イベント運営者が知っておくべき情報を幅広く解説しました。
「喉が渇く前に飲む」「危険な暑さを避ける」「異変に気づき、すぐに対応する」——これらの基本原則を、参加者とスタッフ全員が共有し、実践できる環境を整えることが、安全なイベント運営への第一歩です。事前の準備から当日の運用、緊急時の対応まで、多角的な視点から対策を講じることで、予期せぬ事態にも冷静に対応し、参加者全員が心からイベントを楽しめる状況を作り出すことができます。
イベント実施の際に、会場がアクセスしにくい場所にある場合や、ゲストを送迎したい場合など、移動手段にお困りの場合は、貸切バス手配サービスの「バス旅ねっと」にお任せください。全国に業界最大級の提携バス会社を持ち、大手企業や官公庁などの豊富な実績がありますので、開催地が複数に渡るイベントや定期開催されるイベントも、専任担当に相談いただくだけで最適なバス手配が可能です。スケジュールが決まられている場合は、お見積りフォームからのお問い合わせがスムーズです。